淺沼組の若手社員たちがさまざまな分野の専門家に会いに行き、対話を通して未来の「良い循環」のあり方を考えていく「GOOD CYCLE TALK」。
今回お話を伺ったのは、国内外で開かれる子ども向けの防災フェス「イザ!カエルキャラバン!」や在宅避難のマニュアル本『防災イツモマニュアル』をはじめ、防災関連の様々なプロジェクトを企画・運営するNPO法人プラス・アーツ理事長の永田宏和さん。
地域に根付き、持続する防災教育のためには、どんなことが必要なのでしょうか。ちなみに永田さん、実はゼネコン出身者。そんな“建てる”立場の視点からは少し辛辣な意見もありつつも、自分たちの事業を振り返る貴重な機会となりました。
NPO法人プラス・アーツ理事長/デザイン・クリエイティブセンター神戸センター長 永田宏和 NPO法人プラス・アーツ理事長。兵庫県西宮市生まれ。大学で建築を学び、大学院ではまちづくりを専攻。大手ゼネコンに勤務した後、企画プロデュース会社「iop都市文化創造研究所」を設立。「イザ!カエルキャラバン!」の開発をきっかけに2006年NPO法人プラス・アーツを設立。2012年よりデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)の副センター長、2021年4月よりセンター長を務める。主な企画・プロデュースの仕事に、「水都大阪2009・水辺の文化座」、「イザ!カエルキャラバン!」(2005~)、「地震EXPO」(2006)、「ちびっこうべ」(2012~)、「EARTH MANUAL PROJECT展」(2013~)など。Speaker

阪神・淡路大震災から10年、自分の番がきた
永田さんは兵庫県西宮市のご出身ですが、やはり阪神・淡路大震災が防災教育の原点になっているのでしょうか?

秋山
当時、何かできるとしたら何がしたかったですか?
永田
被災マンションの建て替えとかって、もう壮絶なんですよ。合意形成が図れないので、正解のないことに対して繰り返し説明して納得してもらわないといけない。精神的にやられている同僚もいたりして、とにかく僕も力になりたい。その一心でした。上司に掛け合ってみましたが許可は下りず、また復興ボランティアの活動にも顔を出しましたが、本業が忙しくなり通えず。結果、なんの役にも立てなかったんです。
それは忘れられない出来事でしたね…。その後独立されて、建物の設計やまちづくりコンサル、またアートイベントの企画運営を行うようになったんですね。
永田
そうですね。ただ、防災を始めたのは必然ではなく、言わば偶然でした。震災から10年が経過した時、県と市による「震災10年神戸からの発信事業」というプロジェクトの実行委員会から、子ども向けのイベントをやってほしいと声がかかって。やっと自分の番がきた……と、当時の感情が湧き起こってきました。
自治体としても、子ども向けの防災イベントの必要性を感じていたんですね。
永田
いや、正確に言うと少し違って。当初、防災というテーマ設定はなく、震災から10年が経過した神戸の街から子どもの元気な姿を発信したい、というのが実行委員会の意図でした。具体的には既に全国で人気があり、集客力のあった「かえっこバザール」というおもちゃの交換会を、市内各所でやってもらいたい、というオファーでした。同じく召集された「かえっこバザール」の創始者の藤浩志さんと打ち合わせに参加した時、担当の方が口にした「前を向くために振り返らない」という言葉に違和感を抱きました。過去を振り返って前を向くことだってできるんじゃないか?と。10年前の教訓をしっかり次世代に引き継いでいくことが、豊かな未来において重要だという議論になりました。そこで、「かえっこバザール」に防災訓練のコンテンツを組み合わせることにしたんです。
そこで「イザ!カエルキャラバン!」が誕生したんですね。偶然の産物とも言えそうな。
永田
そうです。でもそれが結果的にすごく良かった。なぜなら、防災イベントってどうしてもつまらなかったり、仰々しいイメージがあって、人が集まらないのが当然のようになっていた。かたや、「かえっこバザール」はものすごく集客力のあるイベント。合体させたことで、楽しみながら学べる集客型の防災イベントが完成しました。
人を巻き込み、根付かせる秘訣

「イザ!カエルキャラバン!」はこれまで国内外合わせて延べ550回以上開催されています。その広がりの秘訣はなんですか?
永田
その意味では、藤浩志さんの考え方にものすごく学ばせてもらいました。彼の考え方は“オープンソース”が基本なんです。フォーマットを自由に使ってもらうことで、人を巻き込み、最終的にオーナーシップがそこへ移るという考え方。キャラクターのカエルがサルになろうがヤモリになろうが、好きにしてくださいと(笑)。最初はノウハウを伝えたりサポートしますが、最終的には僕たちが手を離せるところまでもっていくのがゴールです。特に海外での支援プロジェクトでは、僕たちは1度しか行けない場合も多い。でもほとんどの国で、熱い想いをもった現地の担い手たちが、その後も精力的に各地で開催し続けています。
秋山
これまで世界21カ国で開催されたそうですが、海外と日本で子どもたちの反応は違いますか?
永田
違いは全く感じません。カエルキャラバンは防災をテーマにした「お祭り」であり、楽しいことが好きなのは万国共通だからです。ただ、海外の子どもの方が圧倒的に盛り上がる、というのはあります。特に、おもちゃやゲームなどを持っている子どもが圧倒的に少ない発展途上国では、普段の遊びが、広場を駆けずり回ったり、サッカーをするなど、とてもシンプルなので、「かえっこバザール」のような集客のための仕組みがなくても、「楽しく学べる防災プログラム」だけで、子どもたちがたくさん集まり、盛り上がって、十分成立しています。
それは忘れられない出来事でしたね…。その後独立されて、建物の設計やまちづくりコンサル、またアートイベントの企画運営を行うようになったんですね。
永田
そうですね。ただ、防災を始めたのは必然ではなく、言わば偶然でした。震災から10年が経過した時、県と市による「震災10年神戸からの発信事業」というプロジェクトの実行委員会から、子ども向けのイベントをやってほしいと声がかかって。やっと自分の番がきた……と、当時の感情が湧き起こってきました。

今こそ在宅避難が必要
コロナ禍では「イザ!カエルキャラバン!」の開催も難しくなったと思います。防災は今、どう変化していますか?
永田
「イザ!カエルキャラバン!」は、接触を最小限にするなど工夫し、昨年度、国内では約10ヶ所で行いました。海外では、僕ら講師陣がフルリモートで参加しながら、台湾で全10回のオンラインワークショップを開催し、台湾イザ!カエルキャラバン!の開発支援を行いました。また、企業が発信する防災をテーマにした動画の企画制作や、日本科学未来館で開催された災害の危機から脱出する体験型ゲームの監修なども行いました。色々な制約はありますが、防災を伝えたいという全国の熱い思いを持った担い手のみなさんの思いが萎えないように、防災教育や防災啓発の支援事業をやり続けることが大事だと思います。
確かに。コロナ禍であろうがなかろうが、防災は続いていきますしね。
永田
コロナ禍で怖いのはクラスターです。一方、日本ではいま水害が大変な状況になっている。こうした災害時に避難所に被災者が殺到したら、新型コロナウイルスのクラスターがあちこちで起きてしまう。なので、以前から訴えてきた在宅避難・分散避難の必要性を、もっと伝えていかなければいけないと気づきました。そもそも避難所の環境はよくないのです。阪神・淡路大震災の被災者の多くがそのことを証言しています。トイレが汚いとか、うるさくて眠れないとか、いざこざが起こるとか…。コロナ禍のクラスターのリスクが合わさり、「在宅避難」をより一層強く訴えるようになりました。
確かに、同じようなことが『地震イツモノート』★1にも多数書かれていました。
★1阪神・淡路大震災の被災者167人に聞いた内容をまとめた、防災マニュアル
永田
密を避けるため、自宅や車内で避難生活ができる人はしてください、と。在宅避難を増やさない限り、本当に避難が必要な人も守れなくなります。そこで、在宅避難のノウハウを漏らすことなく詰め込んだ『防災イツモマニュアル』を、2020年4月から大急ぎで着手しておよそ4ヶ月で完成させました。
ハードだけで人は救えない
秋山
近年は世界中で災害が多発し、防災意識の全体的な高まりを感じます。
永田
そうですね。今、防災は時代の潮流です。企業でも、これまではCSR(企業の社会的責任)として防災に取り組む企業が多かったですが、最近の主流はCSV (共通価値の創造)にシフトしています。社会貢献をしながらもビジネスの領域で防災に取り組みたいというスタンスで、参入企業もどんどん増えています。とっても良いことだと思います。

その防災性の高まりは、建物やまちづくりの観点でも感じられますか?
永田
そうですね。建物の防災設備もハイスペックになっています。特にマンションが顕著で、広い備蓄倉庫を設置したり、停電時に共用部だけでなく個々の住居にも一部電気がつくようにしたり。僕が関わったなかで特にすごかったのは、武蔵小杉のタワーマンションです。各フロアに自衛隊や自治体が備蓄するレベルの災害用トイレを導入するなど、これ以上ないくらいの防災関連の設備を投入しました。加えて、購入希望者向けの防災講座を10回以上行い、住人の防災訓練も何年かサポートしました。結果、かなり防災意識の高い人が集まり、入居開始後、防災コミュニティも好調に立ち上がりました。なぜそこまでサポートするのかというと、いくら設備を整えても、ハードだけで人は救えないからです。ハイスペックだから大丈夫、という根拠のない安心感も時に危険です。ゼネコンさんもデベ(デベロッパー)さんも、建てた後のことを考えなきゃいけない。こんな災害の時代において、建てて終わりでは、やっぱり会社としての責任を果たせていない気がします。
「関わりしろ」をどれだけ作れるか?
ゼネコンにいらっしゃった永田さんならではの視点ですね。永田さんが考える、建築における「より良い循環」とはなんでしょうか?
永田
みんなで一緒に作ること、でしょうか。作るところから関わると、愛着もオーナーシップも生まれますし、問題が起きても解決方法がわかる。国際教育の世界でも「物は与えずに一緒に作る」のが主流になっているのは、その方が渡した道具などが故障しても自分たちで直せるからです。そこには、ある種の“確かさ”というか、持続性がある。知識や愛着がコミュニティに循環していくという意味で、一緒に作ることはとても重要だと思います。

栗山
ちょうど今、名古屋支店のリニューアルを行っていて。建設の残土を再利用した素材で、社長も社員も一緒になって土壁を塗っているんです。確かに社内の距離感が縮まっていくのを感じます。
永田
まさに「一緒に作る」の良い例ですね。
秋山
それはレジデンスやオフィスだけではなく、商業ビルや学校、物流倉庫など、どんな建物にも当てはまりそうです。
永田
今、人付き合いが多くの人の課題になっています。以前、あるマンションの住人コミュニティを醸成するため、敷地内に立つ大きなむくの木にあやかって、集会室を「むくの木カフェ」と名付けたことがあります。さらには、カフェの壁や床を住人同士で貼りたかったのですが、デベさんの許可が下りず。でも家具だけは、とお願いして、ワークショップ形式で住人みんなで家具を作りました。完成後にイベントを開くと、常に8割型の住人が出てくれるような、濃いつながりができました。こうした結果が出たのも、デベさんの英断があったからこそ。
秋山
今、とある開園中の幼稚園を施工していて。2棟ある内の1棟ずつを解体し新築する、というのをやっていて。担当の所長がアイデアマンで、例えばクレーンはキリン、土工事はもぐら、などと各工種を動物キャラクターにたとえて、それぞれのイラストを(重機に?)園児に見えるように貼っているんです。園でも、各動物のキーホルダーを作って「工事は1人でも欠けたら終わらないんだよ」と言いながら、園児にランダムに渡したりもして。「今日はもぐらさんの工事だよ」と言うと該当する子は「私の番だ」となり、全員が関心を持つようになりました。
永田
とても良いアイデアですね。建物は残るので、人の居場所になる。その意味でも、そんな「関わりしろ」をどれだけ作れるかが、場所の豊かさに繋がると思います。世の中、繋がったら色々なことが学べる良いチャンスが生まれるかもしれないのに、別々に存在していて交わっていないものってたくさんありますよね。僕は「繋ぎのデザインが大切」っていつも言っているんですが、繋ぎ手がいたら、世の中の色々なことがもっと豊かに変わると思います。
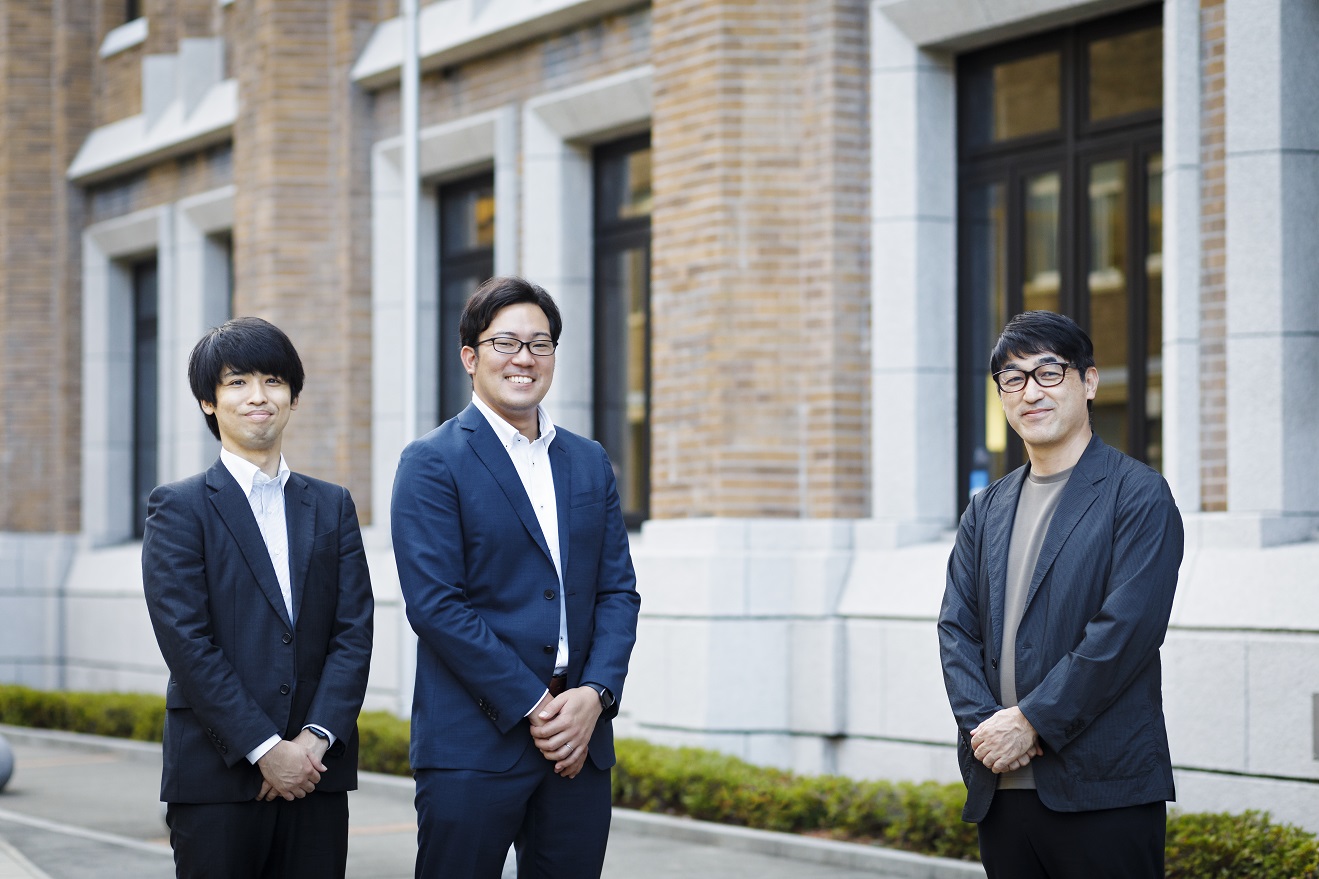
取材を終えて
秋山(大阪本店営業第2部)
永田さんの防災に対する強い想いが、ご自身と周囲の人びとを動かしたのだと感じました。防災教育をはじめるきっかけとなった阪神・淡路大震災から現在に至るまで、その想いは絶えず続いていて、結果としてそれが国内外から求められる企画につながっている。また、良い循環を作り出すためにも、みんなで楽しく作り上げることの豊かさを感じてもらえるような「関りしろ」を私自身も作れたら、と思いました。社会全体の防災意識が向上している今、建設業として、建てた後の責任についても考えなくてはと感じました。
栗山(本社企画部)
建設会社として、優れたハードを提供することが使命ですが、もう一歩踏み込み、例え無駄でも余計でも、そこから何かソフト面の豊かさが生まれるような、目には見えない意識の部分に良い作用を与えられる企業でありたいです。永田さんが感じられたように、いつか「自分の番が来た」時に、最良の選択をできるよう、過去をしっかり振り返りながら、前を向く姿勢を大事にしたいと思います。
撮影:津久井珠美

永田
震災のあった1995年、僕は大手ゼネコンに入社して2年目の頃でした。この会社は、被災地域に竣工物件がものすごく多かった。なので、ゼネコンとしては復旧や復興よりも先に竣工物件の被災調査を行う必要がある。もともと僕は大学・大学院で建築と都市計画を学び、入社時は開発計画本部という都市開発セクションの採用だったので、専門的には“ど真ん中”。あらゆるインフラがマヒしたなか、上司や同僚、また分野の先生方も、みんな調査に奔走されていました。本来であれば僕もその一人になっていたはずなのですが、当時、ちょうど社内のジョブローテーション制度が適用され、設計部に異動し、京都の商業施設の実施設計を担当していたんです。同僚たちが泥まみれになって駆けずり回っているなか、自分はぬくぬくと仕事をして一体何をやっているんだ、と悶々とする日が続きました。